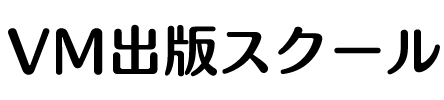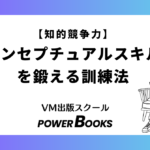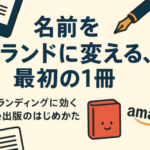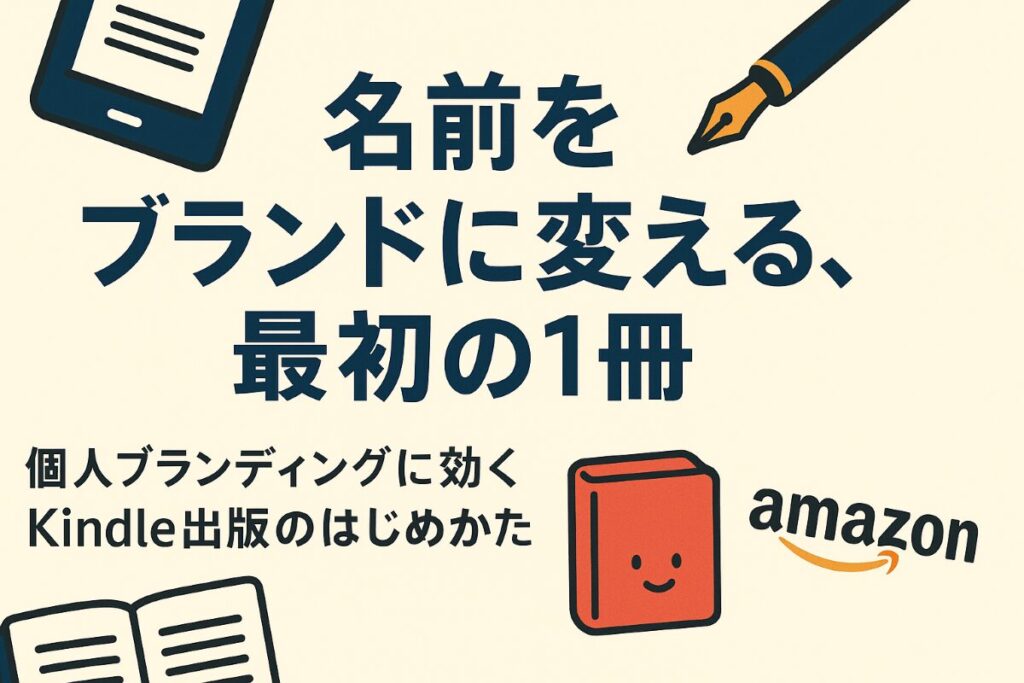
目次
「この人、名前で検索したら本が出てきた」それが信頼になる時代へ
SNSやブログでは限界を感じていませんか?
たとえば、毎日X(旧Twitter)に投稿しても、すぐ流れてしまう。noteで100本記事を書いても、読まれるのは最新の2〜3本。検索に残り、専門性と信頼性をセットで伝えられる“資産”がほしい。そんな方にこそおすすめなのがKindle出版です。
Amazonに自分の著書が並ぶことで、あなたの名前と専門性はセットで認識され始めます。さらに、著者ページができることで“自分メディア”としての立ち位置を確立できるのです。
この記事では、「名前をブランドに変える」ためのKindle出版の活用法と、具体的な始め方をご紹介します。
“名前で仕事を取る”時代がきた
名刺よりも、SNSよりも、Google検索やAI検索で個人の活動実績が調べられる時代。
相手があなたの名前を知った瞬間、検索されることが前提です。
そして検索結果に、あなたの肩書きだけでなく、著書やメディア露出が表示されているとしたら? その時点で「仕事を依頼するにあたり、この人は信頼できる」と判断される確率は飛躍的に高まります。
実際にこんな声があります。
- 「SNSで見かけたあと、その方の本を読んで確信が持てた」
- 「登壇前に著書を読まれていて、話が早かった」
- 「Amazonで本を見つけて、相談を申し込んだ」
名刺代わりになるだけでなく、初対面の前から信頼を築けるのが、出版というメディアの力です。
【当社スクール卒業生の著者の声】
『リーダーのためのメンタルヘルスケア入門』の著者・清水千恵子さんのコメントより
https://vmschool.jp/case/1827/
■出版後に起きたビジネス変化について:
“私は、産業カウンセラーやキャリアコンサルタントとして、研修講師を主な仕事としています。(中略) 1冊目の本を出版した後、研修先の担当者の方が嬉しそうに「先生は本を出されているんですね」と、私の本の表紙と目次を印刷した紙を見せてくれました。正直、驚きましたが、研修講師のことはインターネットで検索するのが当たり前だそうです。これまでは、他の企業の方を含め、講師をする私の名前を検索したけれどヒットせずに、残念な思いをされていたのかもしれません。本を出したことで、研修講師としての信頼を得られたと感じています。”
なぜKindle出版が“ブランディング”に効くのか?
Kindle出版は、ただの電子書籍ではありません。
あなたの名前と仕事を検索でつなぐ「発見される装置」になります。
✔️ 著者ページが自分メディアになる
Kindle本を出すと、Amazonに著者ページを持つことができます。これはいわば「著者=専門家」としてのあなたのプロフィールサイト。あなた自身が出版したAmazonで取扱いのある本や自己紹介、著者写真も掲載可能です。
SNSは流れますが、Amazonは「検索に残る」。
つまり、本を出せばGoogleやAmazonで名前を検索したときに“発見される”のです。
✔️ 本を書く人=専門家 というポジションが得られる
「この人は本を書いている」
それだけで、「この道のプロなんだな」「自分より詳しい人だ」と思ってもらえます。
たとえ中身がシンプルな構成でも、「著者である」事実が専門性と信頼性の証明になります。
✔️ あなたの思想・価値観を体系化して伝えられる
SNSでは断片的な投稿しかできませんが、本は「自分の頭の中を、体系立てて伝える」ことができます。だからこそ、読者は深く納得し、共感し、「この人に相談したい」と思うのです。
Kindle出版は、いわば思考の結晶であり、自分の価値を伝える“濃度の高いメディア”です。
Kindle出版はどのような人に向いているか?
特別な文才がなくても、出版社とのつながりがなくても、Kindleなら個人で出版できます。
では、どのような人がこの方法に向いているのでしょうか?
●SNSは苦手だけど、想いや専門性を伝えたい人
→ 自分のペースで、体系的に伝えられる「静かな発信」に向いています。
●高単価の仕事を取るために「信頼の名刺」が欲しい人
→ 商談・講演・研修などの場面で“著者”というラベルが武器になります。
●登壇・取材・講演などのチャンスを増やしたい人
→ メディア関係者はまず検索します。「著者」であることは重要な選定基準です。
●クライアント獲得やセミナー集客につなげたい人
→ 本がフロント商品となり、出版→読者→相談→受注の流れが生まれます。
Kindle出版の始め方ステップ
ここからは、具体的なステップをご紹介します。
あなたの経験や専門性を「1冊の本」に変える道筋です。
Step1|テーマを決める
「何について書けばいいのか分からない……」
そのようなときは、以下の式がヒントになります。
自分の経験 × 誰かの悩み = 本のテーマ
例:
・自分:会社を辞めて起業した体験
・読者:会社員から独立したい人
→ 「会社を辞めても、収入を得るために必要な5つの準備」など
Step2|章立てを作る(構成化)
章立てのパターンはいくつかあります。たとえば、ビジネス書の王道「課題解決型」であれば、読者が「読みやすい」と感じる流れは以下のようなものです。
1.読者の悩み・現状の共有
2.なぜその悩みが起こるのか(背景・構造)
3.著者の気づきや失敗談
4.解決のための方法・視点
5.実践例・未来の展望
この5章構成をベースに、内容を整理すると書きやすくなります。
Step3|執筆する(生成AIも活用)
「執筆が不安」「書くのが遅い」「パソコン(タイピング)が苦手」
そのような方は、Googleドキュメントの音声入力やChatGPTを使って“原稿のたたき台”を作るのがおすすめです。
・音声を録音し、AIで文字起こし+編集
・自分の過去投稿やメモをAIに渡して構成案を出してもらう
・「この話を本にするとしたらどう構成する?」とAIに聞いてみる
ツールを味方につければ、「書く」ではなく「編集する」感覚で出版できます。
Step4|表紙・校正・出版手続き
出版には「Kindle Direct Publishing(KDP)」というAmazon公式のサービスを使います。
表紙は、Kindle本を手掛けているプロのデザイナーさんに依頼するといいでしょう。表紙はいわば、本という商品のパッケージですから、いい品質のデザインにしたいですよね。VM出版スクールでは複数のプロデザイナーと提携。著者は、自著の目的や読者ターゲット、予算に合ったデザイナーに表紙デザインを依頼することができます。
もちろん自分でデザインができる方であれば、AdobeやCanvaなどのデザインツールを使って、自分で作成もできます。
校正やリライトが不安な場合は、外注やAIツールなども活用してみてください。VM出版スクールでは、ファクトチェックもできる「すごい校正校閲サポート」も提供しています。
「Kindle Direct Publishing(KDP)」に入稿後、24〜72時間でAmazonに反映されて発売開始となります。
印税設定や無料キャンペーンの活用も可能です。
出版後に“ブランディング資産”として活かすには?
出版しただけで終わりではありません。
Kindle本は、あなたの“看板”として活用していくことが重要です。
✅ 名刺・SNSに「著者」の肩書きを入れる
→ 名乗った瞬間の印象が変わります。「あっ!本を出しているんですか?」という反応を得やすい。
✅ Amazon著者ページを自分のポートフォリオに
→ 過去の活動や経歴などのプロフィールを記載できるので、実績紹介になる
✅ 感想をもらって再発信(読者と接点ができる)
→ 読者の声が次の相談・サービスへの導線に
✅ 会社・サービスの信頼性アップに
→ 「この本の著者がやっている会社です」と紹介しやすくなる
まとめ 名前をブランドにする最初の一歩
出版とは、「自分の名前に意味を与える」行為です。
- 「名前を検索したら、本が出てきた」
- 「著者ページに専門分野がまとまっていた」
- 「思いを言語化している姿勢に信頼が持てた」
そんな印象を持ってもらえることこそが、個人ブランディングの真の価値です。
大切なのは、“書けるかどうか”ではなく“書いたかどうか”。
名刺に「著者」と書きたくなる日が、今日から始まるかもしれません。
最後までお読みいただき、ありがとうございます!(VM出版スクール編集部)